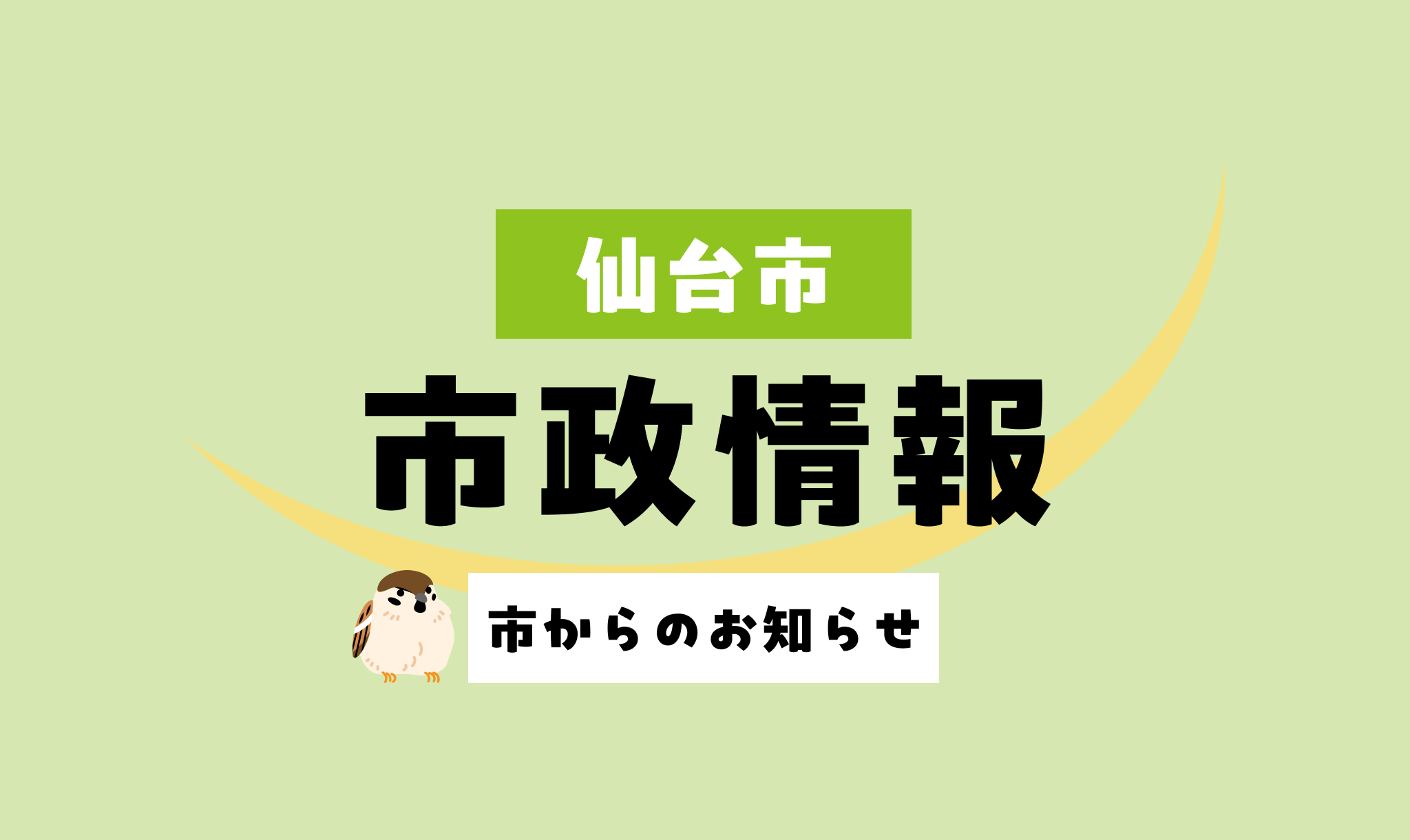子どもの不慮の事故を防ぐためにできること

今月、子どもが足を滑らせて滝つぼに落ちる事故がありました。これから水の事故が増えるので気をつけたいですね。また、自宅の窓やベランダから転落する事故も毎年のように起きています。
子どもは好奇心が旺盛で、危険や加減がわからず行動して、思わぬ事故に遭うことがあります。子どものケガを完全に防ぐことは難しいですが、子どもに多い事故を知り、普段から事故を防ぐ危機意識は持っておきたいですね。2024年以降、国民生活センターや消費生活センターなども呼び掛けている、子どもに多い事故と対策などを紹介します。
■ベランダの転落事故
気候が暖かくなり、窓を開けたりベランダに出ることが増える初夏からは、子どもの転落事故が増える時期。2階からの転落でも、入院が必要な事例が多くあります。

(親ができる予防と対策)
●窓やベランダの手すり付近に、子どもの足がかりになるようなものを置かない。エアコンの室外機は手すりから60cm以上離して設置すること。
●窓や網戸、ベランダの手すりに劣化がないか、安全性を定期的に確認しましょう。
●窓や網戸には、子どもの手が届かない位置に補助錠をつけて、子どもがカギを開けるのを防ぐこと。
●ちょっと外に出るときも、子どもだけを家に残して出ないようにしましょう。
●窓を開けた部屋やベランダで遊ばせない、窓枠や出窓に座ったり、網戸に寄りかかったりしないよう声をかけましょう。
■食べ物による窒息、誤飲、誤嚥(ごえん)事故と予防
子どもは、食べ物をのどに詰まらせて窒息や誤嚥(食べ物や飲み物が気管に入ること)する事故が多いのは、食べ物をかむ力や飲み込む力が大人に比べて弱いから。
特に、飴やラムネ、グミなどのお菓子や豆、ナッツ類、球状の食べ物粘着性が高いもの、固くかみ切りにくいものは窒息につながりやすいので、注意しましょう。

(親ができる予防と対策)
●食べ物は小さく切り分けて少しずつ口に入れましょう。
●よく噛んでから飲み込むように言い聞かせて見守りましょう。
●食事中は姿勢を良くして食べることに集中させます。遊んでいるときや泣いているときには、食べさせないようにします。
●食べ物を喉につまらせて、呼吸が苦しそう、声を出せない、顔色が青くなるなど、窒息が疑われる場合は、すぐに119番に連絡。万が一に備えて喉につまらせた場合の応急措置(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/handbook/content-7/)を覚えておくといいでしょう。
■クーハン(クーファン)からの転落事故
クーハン(クーファン)は、ベビーキャリー、キャリーバッグと言われる、赤ちゃんを寝かせて持ち運びする簡易ベビーベッドのこと。クーハンを動かす際にバランスを崩して、乳児が転落する事故が起きています。

(親ができる予防と対策)
●クーハンを購入する際は、一定の安全基準を満たすSGマークがついているか、実際に乳児を入れてバランスや使用感はどうかなどを確かめましょう。
●取扱説明書の注意事項は必ず読んで、守りましょう。
●クーハンは持ち手を両方バランスよく持ち、乳児が安定した体制で寝ているかを確認します。
●自動車の座席にクーハンをのせることは禁止されています。
■幼児を乗せて自転車に乗る際の事故
自転車に乗せて保育園や幼稚園に子どもを送迎する際、交通事故や店頭、転落、後輪への足の巻き込みなどが起きています。子どもを同乗させる場合は、幼児用座席を使用するか、おんぶをしなければなりませんが、子どもを抱っこして自転車に同乗させた際のケガも起きています。転落して、子どもの頭部が地面に打ち付けられ、打撲したり、頭がい骨骨折や損傷など、重篤なケガにつながります。

(親ができる予防と対策)
●自転車に乗る際は、同乗する全員がヘルメットの着用が努力義務です。自転車に乗る前に必ずかぶせて、シートベルトを締めること。
●子どもを抱っこして自転車に乗ることは道路交通関係法違反です。おんぶ乗車もできるだけ避けて。
●幼児用座席に子どもの年齢、体重、身長が適合しているか、確認しましょう。
●子どもを乗せたり降ろしたりする際は、傾斜や凸凹がない場所で行い、乗せたら手も目も離さず注意を払い、何かあったらいつでも支えられる体制をとること。
●車道と歩道の段差に注意し、段差があるときは速度を落として。
●路面が滑りやすい雨の日は、別な交通手段で移動しましょう。
*****
子どもの事故が起きないように四六時中見守るのは難しいし、限界がありますね。子どもを見守りながら、事故が起こらない環境づくりや体制を整え、何が危ないのか、子どもが自分で気づけるように声がけをしていきましょう。
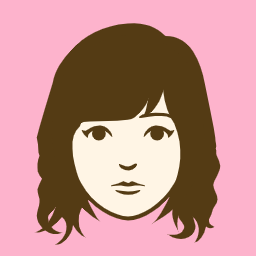
宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、おうちパンマスター、ダイエット検定2級、食生活アドバイザー3級、整理収納アドバイザー2級、エステティシャン初級、ストレッチヨガ講師、小原流華道3級家元教授免許等の資格を「まちのび」で生かせたらうれしいです。