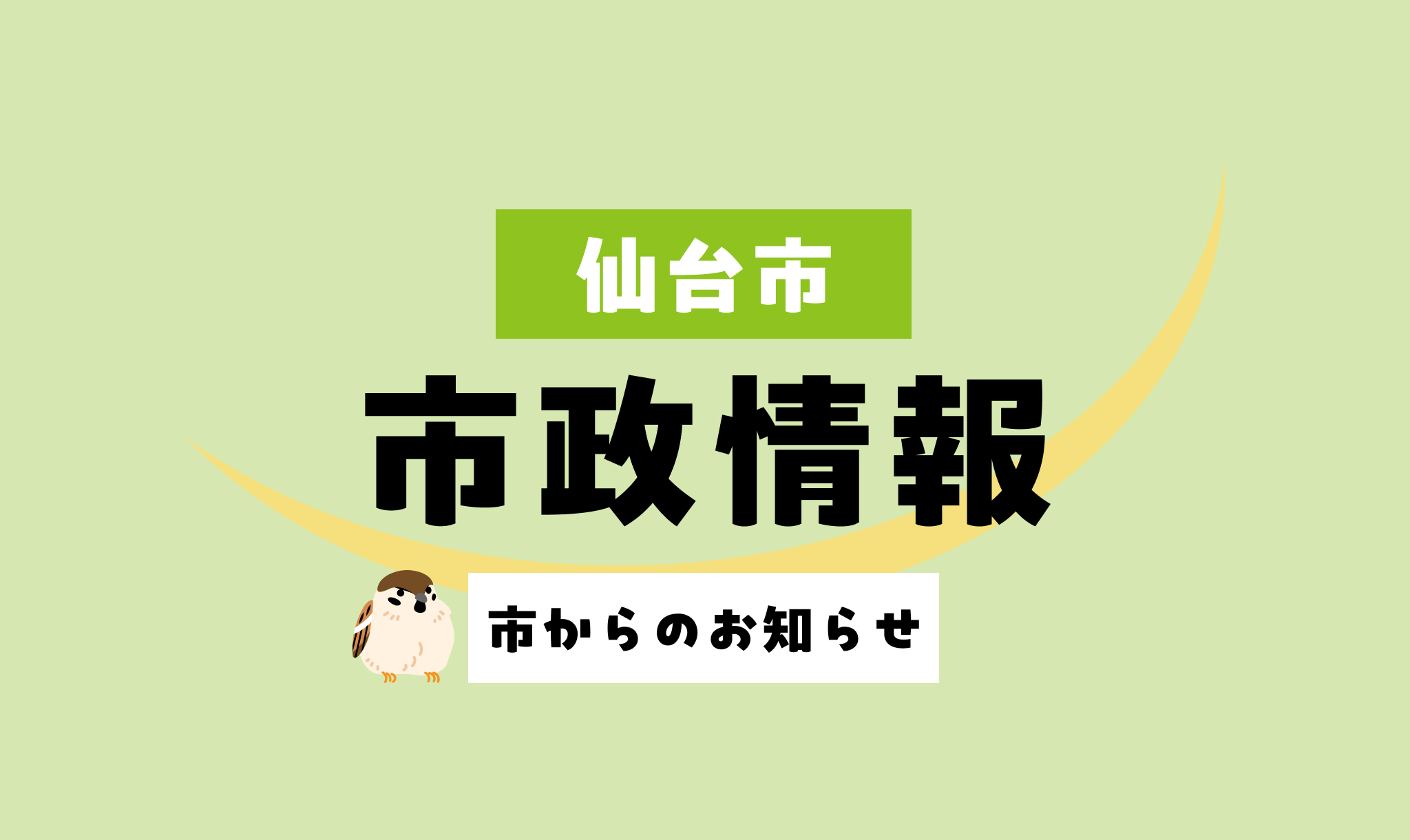ゴールデンウイーク明けの“登園・登校しぶり”との向き合い方

2023年度の不登校の小中学生は、全国で34万6482人で過去最多を記録するなど、親として不安を抱える方も少なくないでしょう。
そんな中でのGW明け、朝の支度をしていると「行きたくない…」と、ぽつりとつぶやく子ども。特にゴールデンウイーク明けには、そんな言葉にハッとするママやパパも多いのではないでしょうか。
Yahoo!ニュースの記事によると、実際にGW明けに不登校になるお子さんも少なくないとのこと。
楽しい連休を過ごした後、再び集団生活に戻ることへの戸惑いや不安が言葉や態度に現れるのは自然な反応です。けれど、毎朝のように泣いて嫌がる姿に、親も戸惑いを抱えるものです。
今回は、そんな時期によく見られる子どもの「行きたくない」にどう寄り添えばよいのか、家庭でできる工夫や心構えをご紹介します。
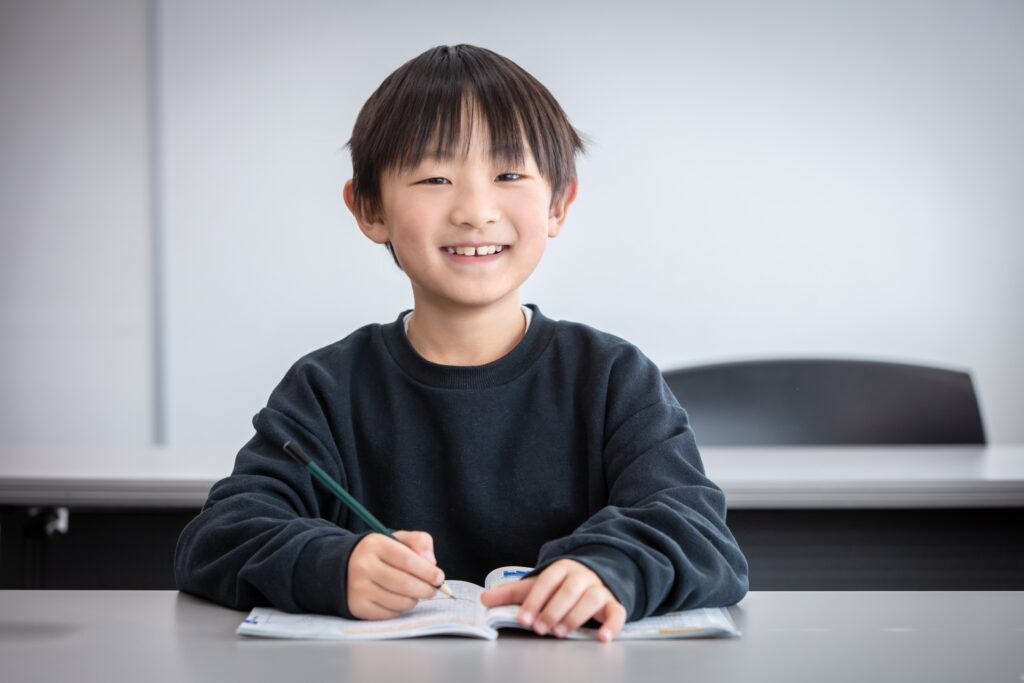
「行きたくない」は子どものSOS?それとも一過性のもの?
まず知っておきたいのは、「行きたくない」という気持ちにはさまざまな理由があるということです。理由を大きく分けると、以下のようなパターンが考えられます。
〇環境の変化による不安や緊張(クラス替え、新しい先生、新しい友だち)
〇長期休暇明けの生活リズムの乱れ(夜更かし・朝寝坊の習慣が抜けない)
〇疲れや睡眠不足、体調不良
〇友だちとのトラブルや園・学校での嫌な経験
〇おうち時間が楽しかった、もっと一緒にいたいという甘え
大人でも、連休明けの出社が億劫になるように、子どもだって「また始まるのか……」という気持ちになるのは自然なことです。すべてを深刻に捉える必要はありませんが、繰り返される場合は慎重な見守りが必要です。
まずは“否定しない”ことからはじめましょう
子どもが「行きたくない」と言ったとき、つい「ダメでしょ」「行かなきゃだめだよ」と返してしまうことがあります。でもまずは、その気持ちを否定せずに受け止めることが大切です。
「そっか、行きたくないんだね」
「お休み楽しかったもんね」
「なんかイヤなことあったの?」
子どもが「わかってもらえた」と感じることで、気持ちが落ち着き、話しやすくなることがあります。大切なのは、すぐに結論を出すのではなく、気持ちの“通訳”になってあげること。言葉で説明しきれない年齢の子どもであれば、表情や態度から察して「ちょっと疲れてるのかな?」「ママともっと一緒にいたいのかもね」と代弁してあげるのも良いでしょう。
保育園や学校と“連携”を取る
子どもが日常的に行きしぶるようであれば、一人で抱え込まず、園や学校と情報を共有することが大切です。親からは見えないところで、子どもがどんな様子で過ごしているのか、先生の目から見た変化や関係性などを教えてもらうことで、安心できる材料が見つかることがあります。
また、先生に「最近、朝になると『行きたくない』と言うようになって…」と正直に相談することで、現場側でも配慮をしてもらいやすくなります。登園後の最初の過ごし方を変えてもらったり、担任以外の先生が迎えてくれるようにしたりするなど、ちょっとした工夫で子どもの不安が和らぐこともあります。

登園・登校前の時間を“安心タイム”にする
登園・登校前の朝の時間が慌ただしいと、子どもにとっては緊張や不安が高まる原因になることもあります。
「時間がないから早くして!」「もう間に合わない!」と親も焦りがちですが、できる範囲で**“安心できるルーティン”**を取り入れてみましょう。
たとえば:
子どもと一緒に朝ごはんをゆっくり食べる
着替えのあとに好きな歌を1曲かける
家を出る前に抱きしめてあげる
「今日は〇〇先生に会えるね」「お友だちと何して遊ぼうか」など、ポジティブな声かけをする
ほんの数分の工夫でも、子どもの心を落ち着かせる助けになります。
あまりに強く拒否する場合は、思い切って1日休ませることも選択肢の一つです。無理に引きずって行かせても、かえって心の負担が大きくなることもあります。
ただし、「休めば何でも解決する」と子どもが覚えてしまうと、次につながらないこともありますので、その日の午後に園や学校に連絡して相談したり、「明日は行ってみようね」と伝えて、次に進むステップを一緒に考える姿勢が大切です。
親自身の気持ちも整えましょう
連休明けは、親も疲れやストレスがたまりやすいタイミングです。「せっかく準備したのに」「また遅刻しちゃう」など、焦りや苛立ちが出てくるのも当然です。でも、子どもは親の感情にとても敏感です。
まずは親自身が「完璧にこなすこと」より「ゆるやかに日常に戻ること」を目指しましょう。深呼吸をして、子どもの気持ちと自分の心に少し余白を持つこと。それが、登園・登校しぶりを乗り越える第一歩になります。
「行きたくない」という子どもの言葉は、親にとっては心配の種ですが、それだけ子どもが今、自分の気持ちを表現できているというサインでもあります。
大切なのは、無理に気持ちを変えさせるのではなく、「今、どんな気持ちなんだろう?」と寄り添い、一緒に日常へと戻っていくことです。連休明けは子どもも親もリズムを取り戻す“助走期間”。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。

大学卒業後、出版社に入社。編集局勤務を経て、1999年よりフリーランスに。以来、「河北新報」「中日新聞」などの新聞、「週刊TVガイド」「S-Style」などのエンタテインメント雑誌、「machinaviPRESS仙台」「河北ウイークリーせんだい」などのフリーペーパー、「手とてとテ」「マイベストプロ宮城」などのウェブ媒体で幅広く執筆活動を続けている。そのほか、観光パンフレット、企業パンフレット、広告コピーなど実績多数。ネットで人気の猫“まる”と“はな”のフォトエッセイ「英語で楽しむ!I am Maru.私信まるです。」(双葉社)では、翻訳と英語解説を務めた。