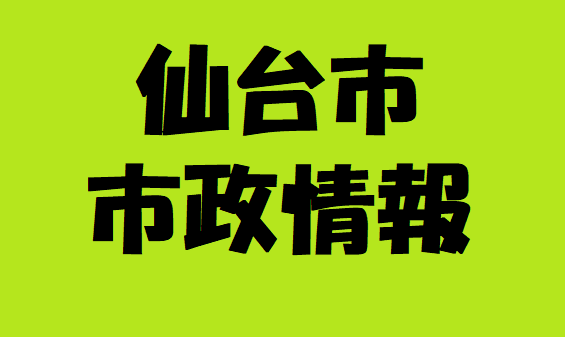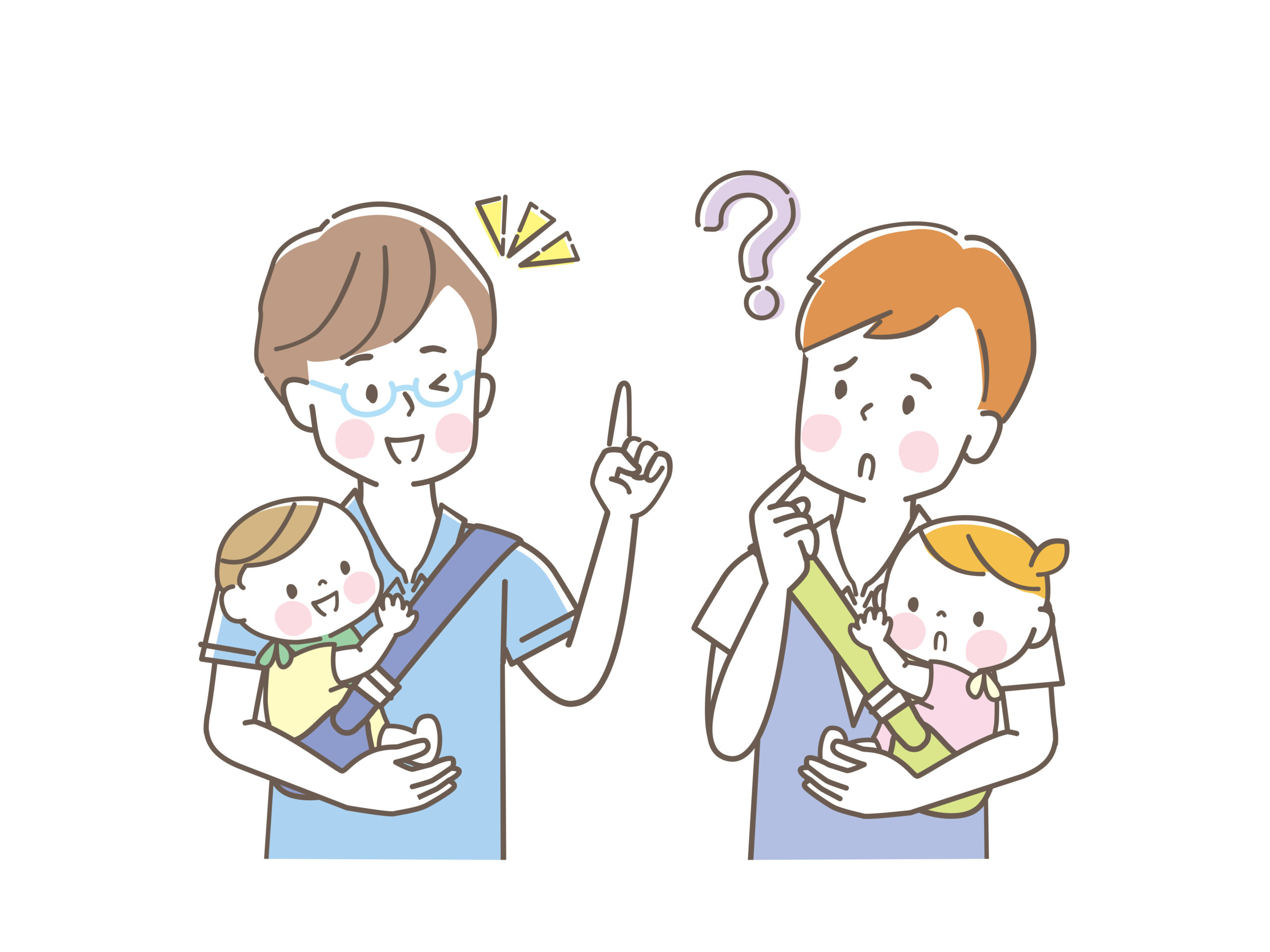お母さんがお子さんに絵本を読んで聞かせる、絵本の読み聞かせは、お子さんの感性や想像力を育み、親子のコミュニケーションにもうってつけですね。今回は、絵本の読み聞かせについて、Family Sitter仙台の髙橋愛さん(あい先生)にお話を聞きました。

髙橋愛さん(あい先生)。保育士・幼稚園教諭の資格を持ち、保育施設で14年間勤務。7歳、5歳の2児の母(写真提供は「Family Sitter 仙台」)
■読み聞かせは生後3カ月ごろからOK
本が好きなご家庭に育ち、子どもの頃は親に図書館や本屋さんによく連れて行ってもらっていたというあい先生。保育士になってからも、好きな本を買って、子どもたちによく読み聞かせをしていました。
「ロングセラーの絵本はやはり長く愛される理由があるし、そういう本を手に取って読むと子どもの頃に戻ったような気持ちになり、やっぱり本はいいなと思います。
うちでは、子どもが日中起きている時間が長くなって、家族の表情を敏感に感じて反応してくれるようになった生後3カ月ぐらいから、本の読み聞かせを始めました。その頃はまだ視力が0.02~0.05程度で良く見えないので、なるべくはっきりと見やすい絵本を、近めの距離でゆっくり読んであげるのがいいと思います。

絵本の読み聞かせのやり方は、子どもを太ももの上に乗せて、子どもと同じ方向から本を読むと、大人の声を心地よく感じながらゆったり見てもらえるでしょう。生後半年位になると、その自分でページをめくったりするようになるので、全部のページが硬い素材のボードブックと呼ばれる本を与えるといいと思います。
訪問しているご家庭で、『本を読んでも、子どもが興味を示さない』というお母さんがいらっしゃいますが、そういうときも、本をなめたり触ったりしながら、本を身近な存在として認識していくので、焦らずに絵本と触れ合えるようにしていくといいと思います。ただ、紙をびりびり破って口の中に入れてしまう危険もあるので、半年位で、一人で過ごすときは与えない方がいいですね。
また、赤ちゃんの頃から図書館に行くのもおすすめです。図書館によりますが、赤ちゃん用の布絵本があったり、靴を脱いでゆったりゴロゴロ過ごすスペースや、授乳室がある図書館もあるので、小さいお子さん連れでも安心です」
■寝る前は布団の中で本を読んであげよう

「『寝る前に本の読み聞かせをすると、目が冴えて遊びだしてしまう』といった声も聞きます。うちでは、本を読んでから寝るのを習慣にしていますが、布団に子どもと一緒に入って、仰向けになって本を読んで、読み終わったら『おやすみ』を言って、そのまま部屋を暗くするとスムーズに寝てくれます。
夜は起き上がって本を読むと、どうしても周りのことが気になって、読み終わった後に布団に入るのを嫌がったりしますが、あおむけで本を読むと、天井と本しか視界に入らないので眠りに入りやすいと思います」
■子どもが本に興味を持つ環境づくり
「子どもが興味をもって本を手に取るには、本棚選びも重要です。背表紙しか見えない本棚より、表紙が見えるようにディスプレイできる本棚、子どもがつかまり立ちをするようになったときに自分で本を出せる高さの本棚がいいと思います。

※イメージイラスト
自分で本を読めるようになるのは、3歳以降だと思いますが、読み聞かせ以外の時間に本を自分で読む時間が増えてきます。うちでは、料理の本や小説、交通安全の本、友達との関わり方、社会ルールがわかる本など、本当に多彩なジャンルの本を置いています。ストーリーのある本ばかりじゃなく、いろんなジャンルの本を置くことで、子どもの興味が広がって、本を読む時間も長くなっていくかと思います。
長男は小学校1年生ですが、漫画の伝記や歴史の本が好きで、読んだ内容を私に要約して話してくれたりして、すごく勉強になりますね。長男が楽しそうに本の内容を話すので、次男もつられて同じ本を読んで、兄弟で本について語り合ったりしています。さらにいろんな知識が広がるように、今後も図書館や本屋さんに親子で通えたらいいなと思います」
本を読むと言葉や表現が増えて、知識や興味が広がり、本を楽しみながら自分なりに考えたり感じたり、読んだ本の感想を自分の言葉で伝えられるようになる、いろいろいい影響があります。そて、本は、家族が一緒に楽しめるコミュニケーションツールでもありますね。
取材協力:Family Sitter仙台
https://peraichi.com/landing_pages/view/kidslinesendaiko