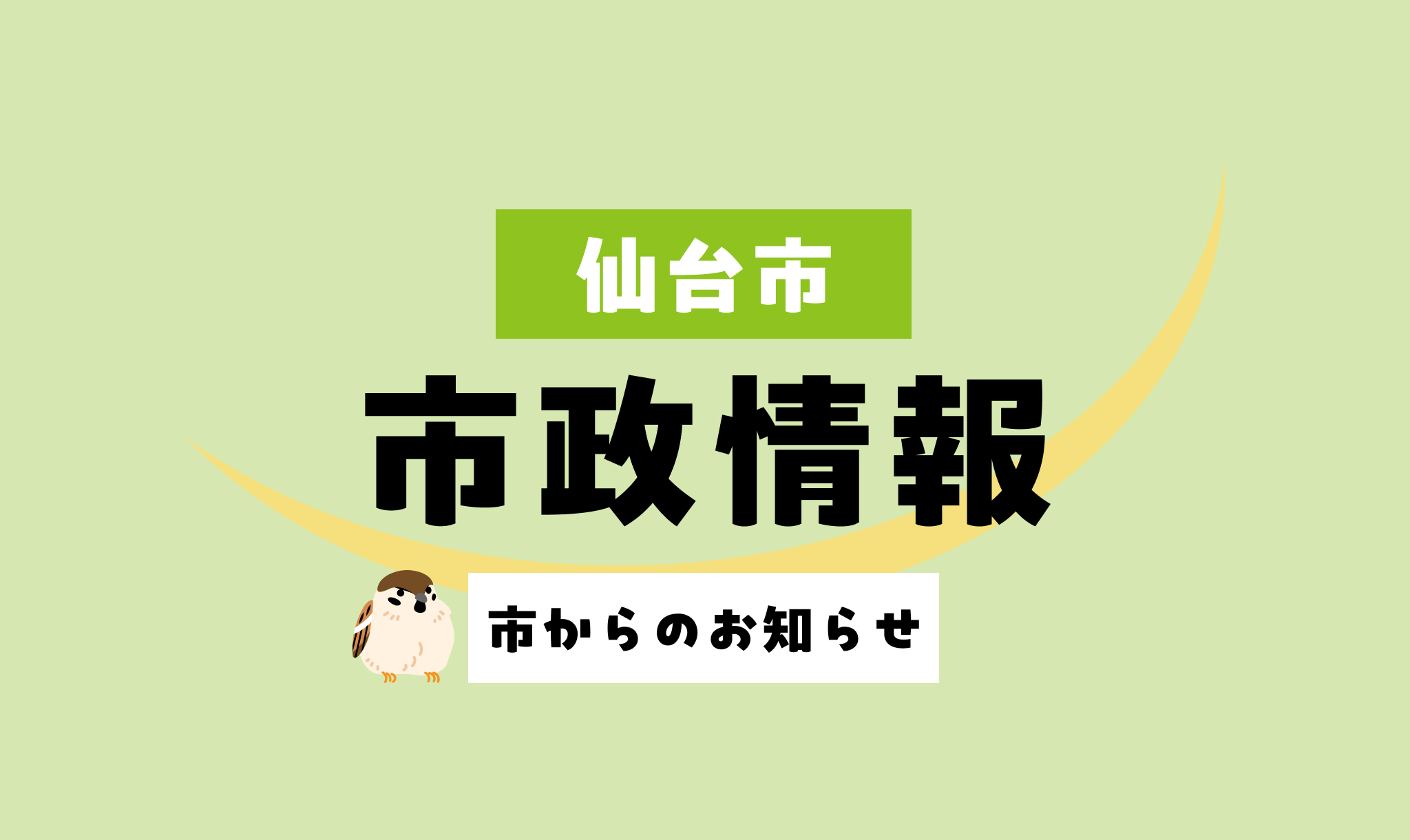小学生にとっての「よい睡眠」とは?

毎日の子育ての中で、「子ども、ちゃんと寝ているかな?」と気になることはありませんか?
特に小学生は、学習、運動、人間関係など、日々の成長に多くのエネルギーを使っています。その土台となるのが「睡眠」です。
最近では、東京大学と理化学研究所などの研究機関も子どもの睡眠に関する研究を行っています。この記事では、小学生の健やかな成長に欠かせない「よい睡眠」について解説します。

小学生に必要な睡眠時間は?
文部科学省や厚生労働省の指針では、小学生の理想的な睡眠時間は9〜12時間とされています。
ところが、実際には95%の児童がこの目安に達しておらず、都市部では特に「夜型」の生活が常態化している傾向もあります。
たとえば、夜9時半や10時を過ぎてから就寝し、朝は7時前に起きて学校へ……というような生活では、睡眠時間が8時間を切ってしまうこともあります。
これが毎日続けば、知らず知らずのうちに「睡眠負債」がたまっていき、集中力や記憶力、感情の安定などに悪影響を与えるおそれがあるのです。
親の影響が大きい?
「厚生労働省による健康づくりのための睡眠ガイド 2023」によると、乳幼児期は、こどもの睡眠習慣が親の睡眠習慣に影響されやすいとのことで、家族ぐるみで早寝・早起き習慣を目指すこと推奨しています。小学生以降は、早起き習慣を保ち、前述の推奨睡眠時間から逆算して、夜寝る時間を決めてみてはいかがでしょうか。小学生になると、夜寝床に入るタイミングを自ら調整する子どもも増えますが、十分な睡眠時間が取れるように親が見守ることも大切です。また、朝食をしっかり食べることも早寝・早起き習慣を保つうえでは重要です。
睡眠不足になると、どうなる?

小学生の睡眠不足は、ただ「眠そうにしている」だけでは済みません。以下のような影響があるとされています:
- 集中力の低下:授業中にぼーっとする、注意が散漫になる
- 感情のコントロールが難しくなる:イライラしやすくなる、すぐに泣く・怒る
- 免疫力の低下:風邪をひきやすくなる
- 肥満リスクの上昇:睡眠不足によりホルモンバランスが崩れ、食欲が増すことも
また、最新の研究では、慢性的な睡眠不足が思春期以降のうつ傾向や不安障害、ADHDの原因となる可能性も指摘されています。
親ができるサポートとは?
では、小学生が質の高い睡眠をとるために、家庭でできることは何でしょうか。ポイントは以下の通りです:
1. 就寝時間・起床時間をできるだけ一定にする
休日も含めて、「毎日同じくらいの時間に寝て起きる」ことが、体内時計の安定に役立ちます。
2. 寝る前のスマホ・タブレットは控える
ブルーライトは脳を刺激し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を妨げます。就寝の1時間前には画面をオフにしましょう。
3. 寝る前の習慣をルーティン化する
たとえば「お風呂→歯みがき→絵本→おやすみなさい」など、毎晩の流れを決めておくと、体が自然と「そろそろ寝る時間だ」と認識しやすくなります。
4. 朝はしっかり太陽の光を浴びる
朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、夜には自然と眠くなるようになります。
成長のカギは「しっかり睡眠」
子どもにとって、睡眠は「休む時間」であると同時に、「学びや感情を整理する時間」でもあります。
学力アップや心の安定を望むなら、まずは「よく眠ること」が基本なのです。
今一度、子どもの睡眠習慣を見直して、家族みんなで「ぐっすり眠れる毎日」を目指してみませんか?

大学卒業後、出版社に入社。編集局勤務を経て、1999年よりフリーランスに。以来、「河北新報」「中日新聞」などの新聞、「週刊TVガイド」「S-Style」などのエンタテインメント雑誌、「machinaviPRESS仙台」「河北ウイークリーせんだい」などのフリーペーパー、「手とてとテ」「マイベストプロ宮城」などのウェブ媒体で幅広く執筆活動を続けている。そのほか、観光パンフレット、企業パンフレット、広告コピーなど実績多数。ネットで人気の猫“まる”と“はな”のフォトエッセイ「英語で楽しむ!I am Maru.私信まるです。」(双葉社)では、翻訳と英語解説を務めた。