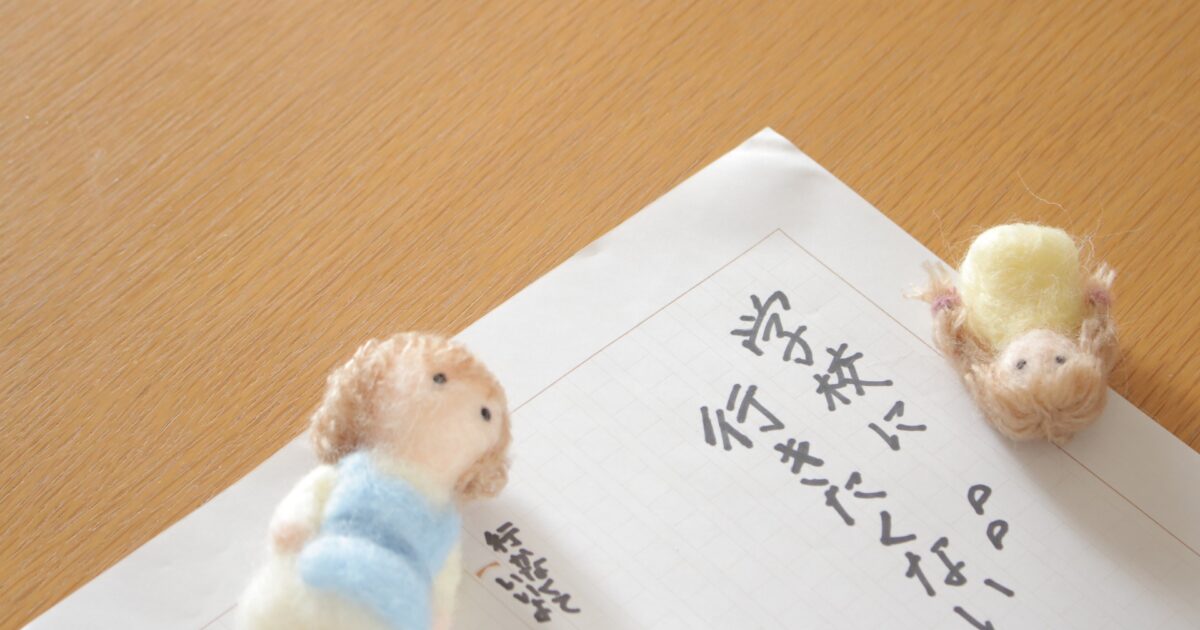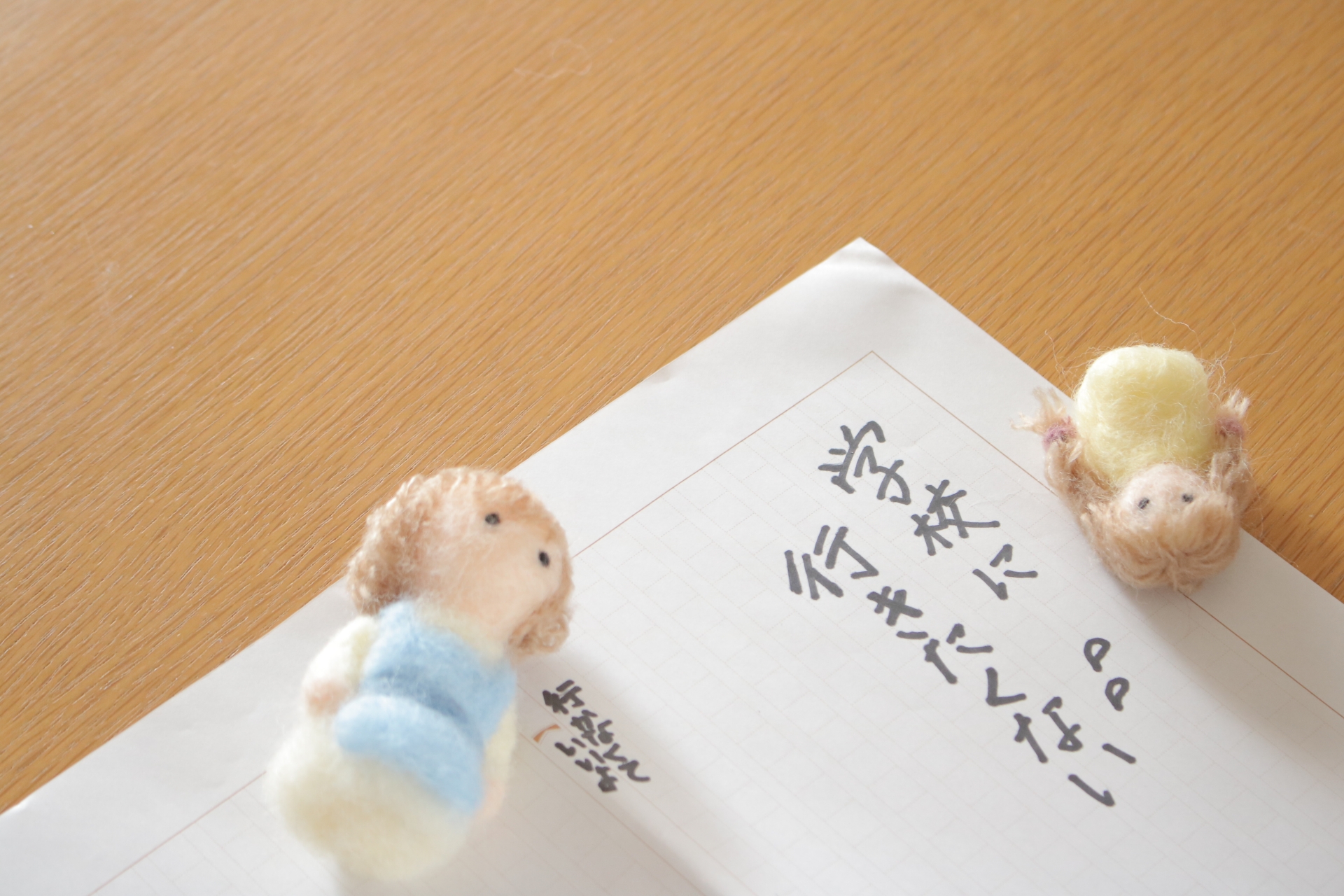長い夏休みを終えると、子どもたちは再び学校生活へと戻ります。友達との再会を楽しみにしている子もいれば、宿題や登校を思うと気持ちが重くなる子もいます。
株式会社NEXERと青山ラジュボークリニックによる調査では、小学生以上の子を持つ保護者の26.8%と約3割の方が、夏休み明けに子どもが学校に行きたがらなかった経験が「ある」と回答しています。
「おなかが痛い」「行きたくない」と言い出す子どもの声に、戸惑う保護者も少なくありません。これは単なるわがままではなく、心の不安やストレスの表れであることもあります。ここでは、夏休み明けに子どもの心を支えるためのポイントを考えてみましょう。
夏休み明けに起こりやすい心の変化
夏休み中は、家族と過ごす安心感や自由な時間がありました。その環境から急に「学校」という社会生活へ戻ることで、子どもは心身に負担を抱えやすくなります。
●生活リズムの変化:夜型の生活から朝型へ戻すことへのストレス
●学習への不安:宿題の遅れや授業へのついていけるかどうかの心配
●人間関係の緊張:久しぶりの友達との再会に対する不安、クラスの雰囲気への戸惑い
●環境変化への抵抗感:長期の休み後は、普段慣れている場所でも「新しいこと」のように感じられる
これらが複合的に重なり、「学校に行きたくない」という言葉や体調不良として表れることがあります。
子どものサインを見逃さない
保護者がまず心がけたいのは、子どもの小さなサインを見逃さないことです。
●朝になるとお腹が痛い、頭が痛いと言う
●前日の夜から「明日行きたくない」と口にする
●食欲が落ちる、眠りが浅い
●イライラしやすくなる、感情の起伏が激しい
こうした変化は、心の不安が体や態度に表れている可能性があります。無理に「大丈夫」と決めつけず、まずは耳を傾けることが大切です。

保護者ができる声かけの工夫
不安を抱える子どもにとって、最も安心できるのは家庭です。保護者の声かけひとつで、子どもの気持ちは大きく変わります。
●「行きなさい!」ではなく「一緒に頑張ろうね」と寄り添う言葉を
●「学校は楽しいでしょ?」と決めつけず、「どんなことが不安?」と聞き出す
●「明日全部できなくても大丈夫、少しずつでいいよ」とハードルを下げる
子どもは「理解されている」と感じることで、気持ちを落ち着け、安心感を持つことができます。
小さな成功体験を積ませる
夏休み明けの登校は、子どもにとって大きなハードルです。だからこそ、「できた!」という小さな成功を積み重ねさせることが効果的です。
●最初は「教室まで行く」「朝だけ顔を出す」でもよい
●登校後に好きなおやつや遊びを用意して、「行ったら良いことがある」と思える工夫をする
●宿題や学習は一気に完璧を目指さず、できるところから始める
達成感が自信となり、次へのステップにつながります。
保護者自身の心構えも大切
子どもの不安に向き合う保護者も、プレッシャーを感じがちです。「うちの子だけ?」「親の接し方が悪いのでは?」と悩むこともあるでしょう。しかし、夏休み明けに登校しぶりを見せるのは決して珍しいことではありません。
保護者自身も「無理に解決しなくてもいい」「少しずつでいい」と考え、完璧を目指さないことが大切です。必要に応じて学校や担任、スクールカウンセラーに相談し、家庭だけで抱え込まないようにしましょう。
子どもが「行きたくない」と口にするのは、心のSOSです。それを「弱い」と切り捨てるのではなく、「そう感じることは自然なこと」と受け止めることから始めましょう。
●子どもの気持ちを否定せず受け入れる
●一緒に解決方法を考える姿勢を持つ
●無理なく小さな一歩を踏み出せる環境をつくる
親が隣で伴走してくれるという安心感こそが、子どもの背中を押す大きな力になります。
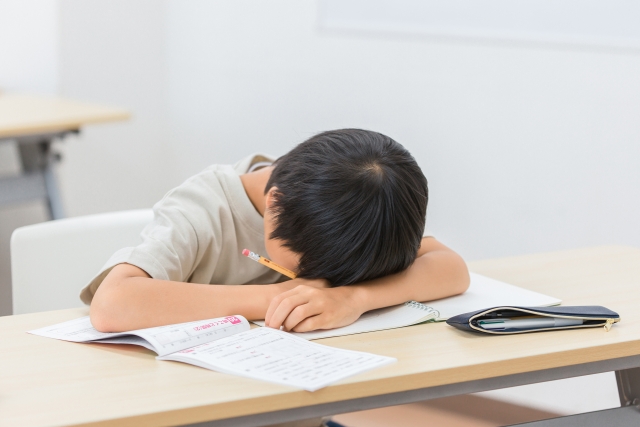
夏休み明けは、子どもにとって心の負担が大きい時期です。「行きたくない」という言葉や体調不良は、不安やストレスのサインかもしれません。
●心の変化やサインを見逃さない
●否定せず受け止め、安心できる声かけを心がける
●小さな成功体験を積み重ねる
●家庭だけで抱え込まず、学校や専門家に相談する
これらを意識することで、子どもは少しずつ自信を取り戻し、新学期の生活に馴染んでいけるでしょう。保護者にできる最大のサポートは、「一緒に歩む姿勢」を示すことです。その伴走があれば、子どもは安心して前へ進むことができます。