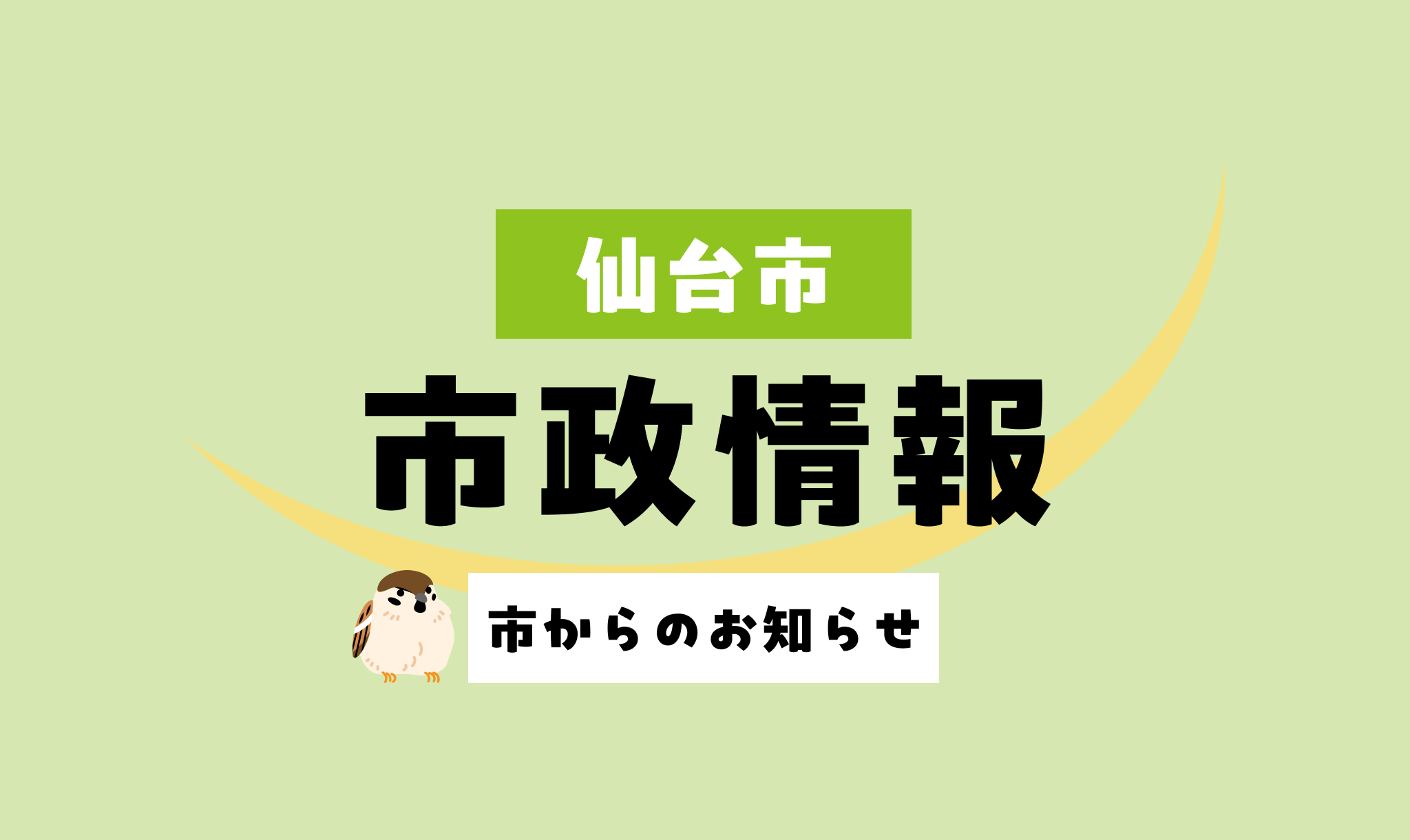子どもの好き嫌いへの対応はどうする?

1~3歳ごろの子どもがご飯を食べないとき、好き嫌いや偏食をするとき、親としては心配になりますが、それも成長過程では自然なことで、誰でも通る道です。子どもはなぜ好き嫌いをするのか、楽しく食事を食べてもらうにはどうしたらいいのでしょうか。保育士・幼稚園教諭経験豊富な「FamilySitter仙台」のみさき先生に、好きじゃないものを食べてもらう対策を教えてもらいました。
■子どもが本能的に好まない味がある
「子どもがご飯を食べない理由のひとつに、生まれ持った味覚があります。例えば、ご飯のようにエネルギー源になる『甘み』、肉や魚に含まれるタンパク質系の『旨味』、ミネラルの存在を教える『塩味』は人間が本能的に好む味覚で、好んで食べることが多いです」とみさき先生(以下、コメントはすべてみさき先生)

みさき先生。幼稚園教諭約5年、保育士約6年経験後、FamilySitter仙台のスタッフとしてママの家事や育児をサポート
「一方、『酸味』は腐敗した味、苦みは毒の味と本能的に感じるため、酸っぱい味や苦い味が苦手なのは人間の本能だから仕方がない、ととらえるしかないと思います。
ただし味覚は発達していくので、いろいろな食材を食べる経験を重ねていくと、さまざまな味を受け入れられるようになって、少しずつ食べられるものが増えていきます。特に1歳~3歳ごろのお子さんは、好き嫌いが固定されていないので、無理強いしないで、根気よく誘いながら試す機会を増やしていきましょう」
■飲み込みやすい、食べやすい調理方法でひと工夫
「また、規則正しい生活サイクルで食事をして、空腹と満腹感のリズムを育てていくことも大事です。そして、食事をしながら『おいしいね』『もぐもぐ上手だね』『これはなんだろうね』など、興味を持たせるような言葉掛けをして、子どもが楽しく食べられる雰囲気をつくりましょう。

子どもが特定の食べ物を食べるのが嫌になる原因として、口に入れて不快に思った経験が大きいので、食べやすくなるようにひと工夫することも大事です。
例えば、塊肉やエビ、こんにゃく、かまぼこ、きのこは、弾力性が強く、噛んでもなかなか細かくならず飲み込みにくいです。イカやエビはすり潰して調理したり、塊肉は小さくカットして噛みやすくしましょう。

また豆やトマトなどのように皮が口に残るものはあらかじめ皮を取っておく。レタスやワカメ、きゅうりの薄切りのようにペラペラしたものは、食材によって柔らかく加熱したり、他の食材と合わせて調理するなど、ひと工夫が大事です。また、パンやゆで卵、さつまいもなど唾液を吸う食材は口が乾いて、口の中に残るので、水分を与えながら食べられるようにしましょう。こうして食材にひと工夫加えることで、誤飲や喉のつまりなどを防ぎ、食事の安全性にもつながっていくところです」
■子どもの成長過程で大切な手づかみ食べ
「2歳ごろになるとスプーンやフォークなどを使い始めますが、まだうまく扱えず、食べ物をこぼしたり、ぐちゃぐちゃにしてしまったりすることも多いでしょう。見ていると『遊んでいるのかな?』と思うこともあるかもしれません。 しかし、食べ物を手でつかんで口へ運ぶ『手づかみ食べ』は、口と手の距離感をつかむ感覚や、手指の動き・握り方・手首の返しなどを身につける大切な経験です。これはスプーンやフォークをスムーズに使えるようになるための基礎的なトレーニングでもあります。

多少の汚れは気にせず、おおらかに見守りながら、たくさん指を使える環境をつくってあげましょう。
また、スープやおじやのように食材を混ぜてドロドロにすると食べやすくはなりますが、慣れてきたら食材ごとの味や食感を感じられる形にしてみるのもおすすめです。一つひとつの味を経験することで、咀嚼力や食への興味が自然と育っていきます。

スープやおじやのように食材を混ぜてドロドロにすると子供は食べやすいですが、徐々に、食材ひとつひとつに愛情を感じられるように、まずはそれぞれの味を試して経験してもらって、咀嚼力を育てていきたいですね」
取材協力:Family Sitter 仙台
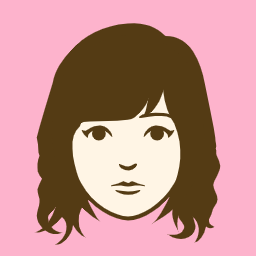
宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、おうちパンマスター、ダイエット検定2級、食生活アドバイザー3級、整理収納アドバイザー2級、エステティシャン初級、ストレッチヨガ講師、小原流華道3級家元教授免許等の資格を「まちのび」で生かせたらうれしいです。