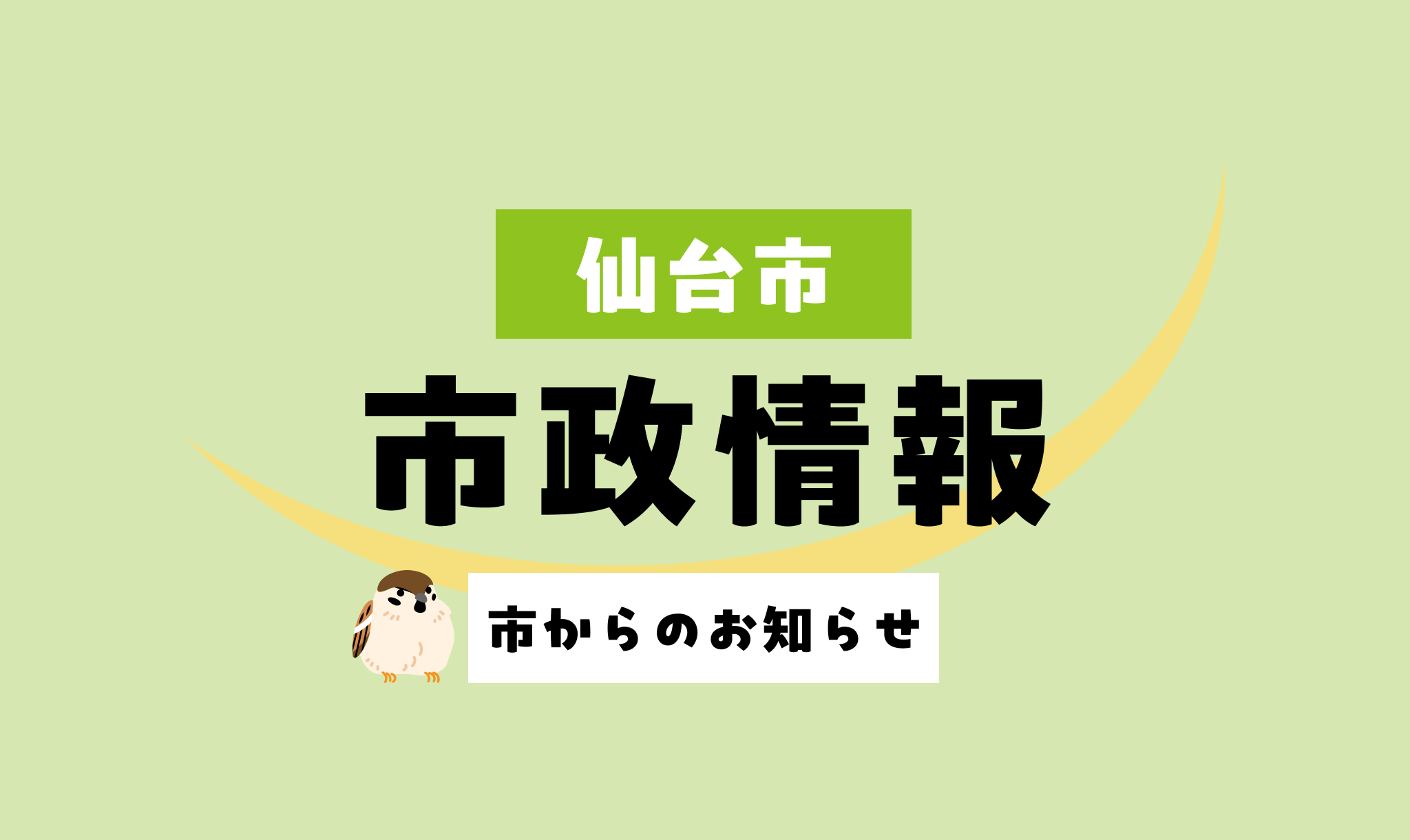秋の夜長に親子で読みたい絵本&物語特集

秋は日が暮れるのが早くなり、夜の時間が長く感じられる季節です。夏の間は外遊びやお出かけに夢中だった子どもたちも、秋になると家の中で過ごす時間が少しずつ増えてきます。そんな「秋の夜長」は、親子でじっくりと本に向き合うのにぴったりのひとときです。読み聞かせは子どもの想像力を育み、心を落ち着ける効果もあります。また、親子で同じ物語を共有することで、会話が広がり、思い出としても心に残ります。今回は、秋におすすめの絵本や物語をご紹介します。
月や星にまつわるお話
秋といえば、お月見や星空観察を楽しむご家庭も多いのではないでしょうか。夜空を題材にした絵本は、子どもの好奇心を刺激してくれます。
例えば『おつきさまこんばんは』(林明子・作)は、小さな子どもでも楽しめる定番の絵本。夕暮れから夜に変わる空とともに、月が顔を出すシンプルな展開は、寝る前の読み聞かせにもぴったりです。少し年齢が上がったお子さんには『100万回生きたねこ』(佐野洋子・作)もおすすめです。深いテーマを含む作品ですが、夜に静かに読むと心に残る余韻を味わうことができます。
また、夜の間ずっと“銀笛を吹く”という役目の双子の星が、さまざまな出来事に巻き込まれる冒険譚「双子の星」(宮沢賢治・作)も、ぜひ読んでほしい作品。宮沢賢治らしいユニークでかわいらしくて愛おしさのあふれる言葉はきっと心に深く残ることでしょう。
秋の自然や収穫を描いたお話

秋は実りの季節。お米、新米、果物、木の実など「食べもの」が身近に感じられる時期でもあります。こうした食や自然をテーマにした本は、子どもたちに季節の移ろいを伝えるきっかけになります。
『14ひきのあきまつり』(いわむらかずお・作)は、大自然のなかで暮らすねずみの家族が秋祭りを楽しむ様子を描いた人気シリーズ。どのページにも秋の色合いが広がり、細かな絵をじっくり眺めることで、子どもとの会話も弾みます。また『ぐりとぐらのえんそく』(なかがわりえこ・文 やまわきゆりこ・絵)は、秋の遠足とおいしいごちそうをテーマにしていて、読み終えた後に「今度のおやつは何にしよう?」と楽しい話題につながること間違いなしです。
行事にまつわるお話
秋にはお月見、七五三、地域のお祭りなど、行事が多くあります。絵本を通じて子どもに行事の意味を伝えると、実際の体験がより豊かなものになります。
『つきみだんご』(高野紀子・作)は、お月見の夜におだんごを作る子どもたちの姿を描いた絵本で、昔ながらの行事をわかりやすく知ることができます。また、七五三にちなんだ『しちごさんなんてこわくない』(たかどのほうこ・作)は、緊張しがちな行事をユーモラスに描いており、子どもに安心感を与えてくれます。
親子の絆を感じられるお話
夜に読む本は、子どもが安心して眠りにつけるよう、温かさや優しさを感じられる内容のものをピックアップするといいでしょう。
『だいすき ぎゅっ ぎゅっ』(フィリス・ゲイシャイトー&ミム・グリーン・文 デイヴィッド・ウォーカー・絵 福本友美子・訳)は、親子の愛情がシンプルに描かれた名作で、何度もぼうやをギュッと抱きしめるママの姿が心を打ちます。読みながら自然とスキンシップが生まれる一冊となるでしょう。
読み聞かせをより楽しくする工夫
読み聞かせをするときには、ただ文字を読むだけでなく、登場人物の声を変えたり、絵を一緒に眺めたりすることで子どもが物語に入り込みやすくなります。秋の季節感を演出するなら、読書の時間にお茶を入れたり、ハロウィンの飾りをお部屋に置いたりするのも楽しい工夫です。また、読み終わった後に「どの場面が好きだった?」と問いかけることで、子どもの表現力や思考力を伸ばすことができます。

秋の夜長は、親子で読書を楽しむ絶好のチャンスです。月や星のお話、秋の自然を描いた物語、行事をテーマにした絵本など、季節感あふれる作品を選ぶことで、読書の時間が一層豊かなものになります。本を通じて子どもが感じたことを共有すれば、親子の会話が広がり、心に残る思い出になるでしょう。今年の秋はぜひ、親子で絵本を開いてみませんか。
次週は、保育士でもある整理収納アドバイザーのお片づけシュガーさんこと、さとうゆみこさんに絵本の読み聞かせについて伺います。お楽しみに!

大学卒業後、出版社に入社。編集局勤務を経て、1999年よりフリーランスに。以来、「河北新報」「中日新聞」などの新聞、「週刊TVガイド」「S-Style」などのエンタテインメント雑誌、「machinaviPRESS仙台」「河北ウイークリーせんだい」などのフリーペーパー、「手とてとテ」「マイベストプロ宮城」などのウェブ媒体で幅広く執筆活動を続けている。そのほか、観光パンフレット、企業パンフレット、広告コピーなど実績多数。ネットで人気の猫“まる”と“はな”のフォトエッセイ「英語で楽しむ!I am Maru.私信まるです。」(双葉社)では、翻訳と英語解説を務めた。