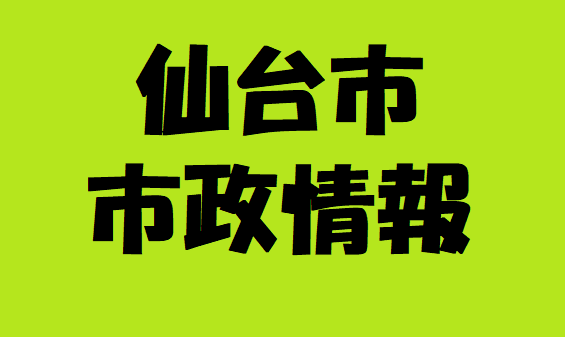離乳食の後は幼児食、そして大人と同じ食事へと段階を踏んで移行していきます。栄養バランスの良い食事を考えて準備しても、子どもが食べてくれなかったり、好きだったものを急に食べなくなったりすると困ってしまいますね。好き嫌いをせず何でもおいしく食べて、すくすくと成長してほしい、と思うのが親心。今回は、子どもが食事食べないときの対策について「FamilySitter仙台」のみさき先生に教えてもらいました。
■子どもが楽しく食べられる雰囲気づくりを
「1歳~3歳ごろのお子さんは、昨日まで食べていたものを今日は食べない、といった場面は結構多く見られます。自分で食べたいけれど、食べさせてもらいたい、そんな相反する気持ちがぶつかるのは、発達の過程でよくあること。成長のひとつのサインと捉え、食べないときは無理に食べさせないで、その日のその時の気分に寄り添うことが大切。一回食べなかったから嫌いと決めつけなくても大丈夫です。ただし、食べないからと最初から諦めないで、『食べてみようか』と誘ったり、ゆるく促すことは必要ですね」(コメントはすべてみさき先生)

みさき先生。幼稚園教諭約5年、保育士約6年経験後、FamilySitter仙台のスタッフとしてママの家事や育児をサポート
「保育園や幼稚園、特に年中さんや年長さんになると、周りの友達が食べてるから負けずに食べようとか、友達がおいしそうに食べてるから食べよう、という子どもが多いようです。家では食べないけど、保育園・幼稚園だとみんなと食べるから食べられる、頑張ってみるといった、友達の影響、周りの影響が大きいと思います」
■味見作戦や実況中継作戦も有効
「子どもと一緒に食事をして、大人が美味しそうに食べる様子を見せることも大事ですね。毎回完食することを目指さずに一緒に楽しく食卓を囲む経験が、食への関心や意欲を育てていくと思います」

「ご飯をつくっているときに、子どもに『ちょっと味見してみて』とすすめてみましょう。食事と違う時間、違う環境で食べることで苦手だったものが食べれたり、おいしいと感じて、その後の食事で食べるようになったりすることがあるので、この『味見作戦』は試してみてください。

また、保育園でトライしていたのは、食べる様子や音などを言葉にして伝えること。キュウリを食べる時に『パリパリ音がするね』とか、スープを飲むときは『ごくごく飲んでるね』といった食べる様子を実況中継すると、子どもたちも『どんな音がするかな』『ごくごくって聞こえたね』などと興味を示して、食べるのを楽しむ様子もあったので、そういう『実況中継作戦』もひとつの方法かと思います。
■ゆったりした気持ちでポジティブな声がけを
「子どもが食べないときに大人が困った顔をしたり表情に出てしまうと、子どもは敏感に感じ取るもの。なので、今日はダメだったけど明日は食べるかな、くらいに気軽な気持ちで取り組むと、子どもたちも楽しい食事につながっていくように思います。特に夕食の準備をする時間は忙しいと思いますが、ゆったりとした気持ちで取り組むといいですね」

「『この間食べなかったの、食べてるね』『ご飯おいしそうに食べたね』『今日は昨日より、もりもり食べてるね』といったポジティブな声がけも積極的に行うといいですね。野菜嫌いでも、スープにすると食べやすくなり、積極的に食べることもあるので、調理法を変えるなど工夫してください。
4歳、5歳ぐらいになると、その食べ物の苦手な理由を説明できるようになって、対策を立てやすくなりますが、1~3歳くらいは、最初に食べたときの印象が良くなかったり、なんとなく好きじゃなかったなどということが多く、好みがまだ安定していません。大人が感じ取っていろいろ工夫してみたり、すぐに食べられるようにならなくても、時間をかけて根気強く続けていくのが一番大切です」
みさき先生のアドバイスを参考に、ゆったりした気持ちで、子どもの気持ちに寄り添いながら、いろいろ工夫してみてくださいね。
■取材協力:Family Sitter 仙台